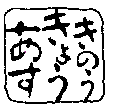新聞で使える漢字は常用漢字が基本。常用漢字以外の漢字は、熟語の一部でも平仮名を混ぜたり、ルビを振る。新聞は万人が読めることを前提にしているからだ。
しかしエッセイとなると、それでなければという思いが書き手にあれば、ある程度無視して自由に使ったらよいと思う。
私がどうしてもいやだと思うのが代用漢字だ。常用漢字以外の漢字で、常用漢字と似た字があれば、それで代用してもよいと国語審議会が決めている。たとえば、稀有は希有、擬似は疑似、象嵌は象眼、臆病は憶病、といった類い。漢字の数は膨大で、諸橋轍次の大漢和辞典には、親文字で5万語、熟語で53万語もあるから、これもやむを得ぬ苦肉の策ではあろう。しかし、漢字はそれぞれ固有の意味を持っており、姿かたちが似ているから拝借というのは、いかにも乱暴だ。稀は「まれ」なのに希は「ねがう」、擬は「なぞらえる」なのに疑は「うたがう」の意味しかない。象嵌の「かたどり、はめる」を「象の眼」にしてよいものか。「おもいだす、おぼえる」の憶の病とは認知症のことなのか。
外国語の氾濫もしばしば問題になる。安倍前首相は最初の所信表明演説でカタカナを70回も多用した。「戦後レジームからの脱却」をうたい文句にして全国民に呼びかけたが、レジームの意味が分からず戸惑った人は何千万人いただろう。相手の立場に立てない人は、日本語を使ってもよく伝わらない。「美しい国、日本」とは一体なにを言いたかったのか。
訳語は、あえて訳せばという便宜上のもので、外国語と日本語は厳密に言えば置き換えられない、というのが私の考え方だ。オレンジを訳せばみかんになるが、愛媛で採れるのはみかんで、カリフォルニアで採れるのはオレンジでなければならない。2つは大きさも皮の厚さも味も全然違う。
ずいぶん理屈っぽい話になってしまったが、私が言いたいのは、言葉や言い回しを選ぶときは、場面に応じて一番ぴったりするものを選ぶべきだということだ。やわらかい和語、硬い漢語、くだけた俗語、軽い流行語、カタカナ、平仮名……字数の少ない俳句や短歌の世界では、とりわけ言葉選びが命となる。
文をつづる途中で、もっと適当な言葉や言い回しがあったはずだが、筆を止めて探してみても思い浮かばない、というときがある。そんなときはとりあえず書き進んでひと晩置き、翌日読み直してみると、見つかりやすい。